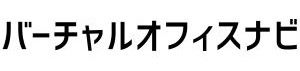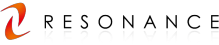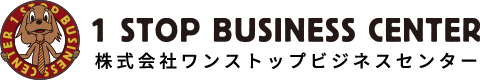「副業を法人化したいけど、会社にバレるのが不安」と感じていませんか?
この記事では、副業を法人化する際に会社にバレる主な原因と、バレないための具体的な対策を徹底解説します。
今すぐ読み進めて、成功する法人化への第一歩を踏み出しましょう。
副業を法人化すると会社にバレる主な原因
- 住民税の増加による発覚
- 社会保険関連の通知
- 情報の口外やSNSでの発信
- 法人登記情報の公開
- 金融機関や税理士からの連絡
住民税の増加による発覚
副業で得た収入により住民税が増加し、その情報が勤務先に通知されるため。
副業の収入が年間20万円を超える場合、確定申告が必要となります。
確定申告後、住民税の額が増加し、勤務先に通知が届くことで、副業が発覚する可能性があります。
社会保険関連の通知
副業の法人から役員報酬を受け取ることで、社会保険の加入義務が生じ、関連通知が勤務先に届くため。
副業の法人から役員報酬を受け取ると、社会保険への加入が義務付けられます。
この際、年金事務所から「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」などが勤務先に送付され、副業が発覚するリスクがあります。
情報の口外やSNSでの発信
同僚や上司への口外、SNSでの投稿などから情報が広まり、副業が知られるため。
副業の状況を同僚や上司に話したり、SNSに投稿したりすることで、その情報が広まり、勤務先に伝わる可能性があります。
法人登記情報の公開
法人登記情報が公開され、勤務先がそれを確認することで、副業が発覚するため。
法人を設立すると、会社名や所在地などの情報が公開されます。
代表者名は記載されないことが多いですが、会社名や所在地から勤務先に副業が知られる可能性があります。
金融機関や税理士からの連絡
融資の申し込みや税理士とのやり取りの際、勤務先に連絡が入ることで、副業が発覚するため。
法人設立後、金融機関からの融資や税理士との連絡が勤務先に届くことで、副業が知られるリスクがあります。
副業を法人化して会社バレないための対策
- 役員報酬を受け取らない
- 家族を役員にして報酬を支払う
- 法人登記情報の工夫
- 住民税の納付方法の選択
- 情報の取り扱いに注意する
役員報酬を受け取らない
設立した法人から自分自身が役員報酬を受け取らないことで、個人の所得が増加せず、住民税や社会保険料の変動を防ぎます。
役員報酬を受け取らなければ、個人の住民税や社会保険料に変化が生じないため、会社に通知が行くリスクを回避できます。
家族を役員にして報酬を支払う
信頼できる家族を法人の役員として任命し、その家族に役員報酬を支払うことで、自分自身の所得増加を避けます。
家族が役員報酬を受け取ることで、自分の所得や社会保険料に影響を与えずに法人の利益を分配できます。
法人登記情報の工夫
法人の登記時に、会社名や所在地に個人名を含めない、所在地を自宅以外に設定するなどの工夫を行います。
登記情報から個人と法人の関係を特定されにくくすることで、会社にバレるリスクを低減できます。
住民税の納付方法の選択
副業の所得に対する住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」に設定します。
住民税を自分で納付することで、本業の会社に副業分の住民税情報が通知されるのを防げます。
情報の取り扱いに注意する
副業や法人設立に関する情報を同僚や上司、SNSなどで不用意に共有しないようにします。
口外やSNSでの発信から情報が広まり、会社に伝わるリスクを避けるため、情報管理を徹底します。
副業を法人化する主なメリット
- 節税効果
- 社会的信用の向上
- 経営リスクの限定
- 資金調達の幅が広がる
節税効果
法人化により、個人よりも税率が低い法人税を適用でき、所得分散や経費計上の幅が広がるため、節税が可能です。
社会的信用の向上
法人化することで、取引先や金融機関からの信用度が高まり、ビジネスチャンスの拡大や資金調達がしやすくなります。
経営リスクの限定
法人は有限責任であるため、万が一事業がうまくいかない場合でも、個人の資産への影響を最小限に抑えることができます。
資金調達の幅が広がる
法人化により、融資や助成金の対象となりやすく、事業拡大のための資金調達が容易になります。
副業を法人化する主なデメリット
- 設立および運営コストの増加
- 社会保険への加入義務
- 税務調査のリスク増加
- 赤字でも発生する税金
- 会社資産の使用制限
設立および運営コストの増加
株式会社の設立には約25万円、合同会社でも約10万円の費用がかかります。
法人としての運営には、決算申告や税務申告などの手続きが必要で、これらを専門家に依頼する場合、その報酬が発生します。
社会保険への加入義務
法人化すると、社長が常勤役員となる場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が生じます。
税務調査のリスク増加
法人は個人事業主に比べて、税務署による税務調査が実施される頻度が高いとされています。
赤字でも発生する税金
法人化すると、事業が赤字の場合でも「法人住民税均等割」という税金を必ず支払う必要があります。
会社資産の使用制限
法人化により、会社の財産は会社のものであり、社長個人が自由に使うことはできません。
副業を法人化する際の注意点
会社の就業規則の確認
法人化の適切なタイミング
税務申告と社会保険の手続き
住民税の納付方法
会社の就業規則の確認
まず、勤務先の就業規則で副業が許可されているかを確認しましょう。
副業が禁止されている場合、法人化によって勤務先に知られるリスクが高まります。
法人化の適切なタイミング
法人化にはコストや手間がかかるため、事業の利益が一定以上になった段階で検討するのが効果的です。
一般的には、副業の年間所得が約500万円を超えるタイミングが目安とされています。
税務申告と社会保険の手続き
法人化すると、税務申告や社会保険の手続きが複雑になります。
特に、法人税や消費税の申告、社会保険への加入義務などが発生します。
これらの手続きを適切に行わないと、ペナルティの対象となる可能性があります。
住民税の納付方法
副業の所得に対する住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」に設定することで、本業の会社に副業が知られるリスクを減らせます。
ただし、自治体によっては普通徴収を選択できない場合もあるため、事前に確認が必要です。
副業を法人化するならバーチャルオフィスがおすすめ!
- 自宅住所を公開せずに法人登記できる
- 会社にバレるリスクを減らせる
- 初期コストを抑えられる
- 信用力が上がる
自宅住所を公開せずに法人登記できる
法人を設立すると、登記情報(会社の所在地)が一般公開されます。
自宅を登記すると 「会社名+住所」が誰でも検索できる 状態になり、個人情報が漏れるリスクがあります。
バーチャルオフィスを利用すれば、都心の一等地の住所で法人登記ができ、 プライバシーを守りながらビジネスを進める ことが可能です。
会社にバレるリスクを減らせる
自宅を法人の所在地にすると、郵便物や税務署からの書類が届くことがあります。
もし家族が誤って書類を開封し、それが会社に伝わってしまうと 副業が発覚するリスク があります。
バーチャルオフィスを利用すれば、法人向けの郵便物はすべてオフィス宛てに届くため、こうしたリスクを回避できます。
初期コストを抑えられる
通常、法人化すると オフィスを借りる費用が発生します。
しかし、バーチャルオフィスなら 月額1,000円~5,000円程度 で利用できるため、本業の収入を圧迫せずに法人化できます。
信用力が上がる
バーチャルオフィスは都心の一等地にあることが多く、「東京・銀座」「渋谷」「新宿」 などの住所で法人登記できます。
このため、取引先からの信用度が上がり、個人事業ではなくちゃんとした会社として見られるメリットがあります。

まとめ
副業を法人化する際には、 会社にバレるリスクを抑えながら、コストを抑える工夫が重要です。
バーチャルオフィスを活用すれば、自宅住所を公開せずに法人登記でき、初期費用も節約可能です。
ただし、法人口座の開設や業種ごとの制約にも注意しながら、自分に合ったバーチャルオフィスを選びましょう。